「“海のゆりかご”アマモ場再生講座~アマモの種取り体験編~」を開催しました!
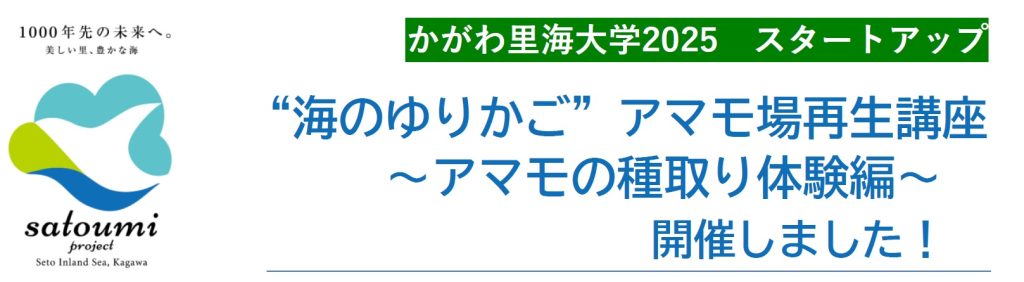


- 日時 令和7年6月22日(日)13:00~16:00
- 会場 交流の里おうごし(坂出市王越町)
- 講師 末永慶寛氏(共創の場形成支援プログラムPL/香川大学創造工学部教授)、谷光承氏(かがわ里海ガイド)
- 講師アシスタント 高橋真央氏(かがわ里海ガイド)
実施内容
6月22日(日)、交流の里おうごしにて坂出市と共催で、「“海のゆりかご”アマモ場再生講座~アマモの種取り体験編~」を開催しました。本講座は、豊かな海を育むアマモについて学び、アマモの増加を目指す全3回シリーズの第1弾として実施されました。当日は大人と子ども合わせて25名の方にご参加いただき、和やかな雰囲気の中で講座が進行しました。開催にあたり、坂出市の有福哲二市長よりご挨拶をいただき、講座の意義や地域の海への期待が語られました。続いて、谷氏よりスライドを交えながら、アマモの種の採取方法についての説明がありました。また、アマモの採取には県知事の許可が必要であるとの説明がありました。その後、末永先生からは研究対象である「藻場」について詳しいお話があり、スライドや映像を通じてアマモが海の生態系に果たす役割や再生の重要性について理解を深めました。その後、アマモが生育する海岸へ移動しました。


〈アマモの花枝採取〉
海岸に到着後、正しいライフジャケットの着用方法と観察時の注意事項について説明を受け、干潮の海に入り、アマモの花枝採取を行いました。アマモは沿岸部の砂泥地に自生しており、水面にはイネのような細長い穂が浮かんでいました。穂をよく観察すると、ふくらんだ部分があり、ぷっくりとしたアマモの種を見つけることができました。次第に花枝を見つけるスピードも上がり、種が多く付いている花枝を選びながら袋に集めていきました。また、アマモ場は“海のゆりかご”とも呼ばれており、アマモ場に棲む生き物の赤ちゃんや、葉に付着した卵を見つけた受講者からは歓声が上がっていました。大人も子どもも夢中になって花枝採取に取り組んでいました。


〈生き物観察と振り返り〉
1時間ほど花枝採取を行った後、アマモ場で見つけた海の生き物の紹介と講座の振り返りを行いました。小さなヒメイカ、ボラの子ども、ゴカイの卵、イカの卵などが見つかり、受講者は触ったり写真を撮るなどじっくりと観察していました。採取した生き物は観察後に海に返しました。最後に、谷氏より「アマモの量が昨年より減少していた。アマモを増加させるために種の選別や種まきを行う講座を開催予定なので参加して欲しい」とお話がありました。
講座終了後のアンケートでは、「アマモの種取りは初めてだったので、貴重な体験になりました」「アマモの種取りだけでなく、藻場に生息している生物についても学ぶことができたため大変満足でした」「アマモは魚にとって大事にしなければならないものと分かった」などの感想が寄せられました。海の生き物や環境にとって重要な役割を果たす藻場について学び、再生活動に参加できたことは、受講者にとって貴重な体験となりました。





