「よく分かる!海ごみ調査講座」を開催しました!
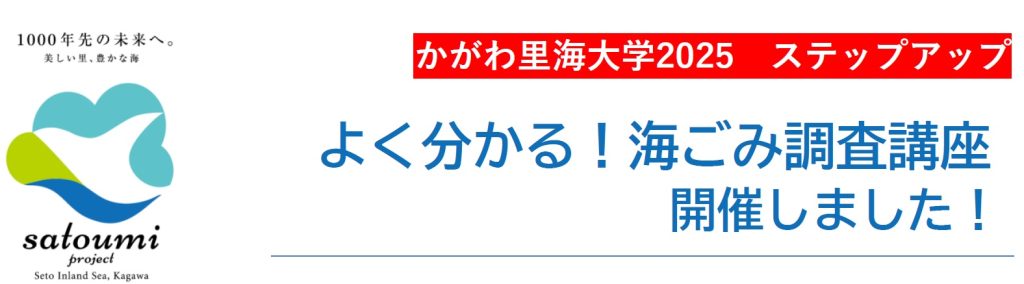


- 日時 令和7年8月2日(土)9:00~11:00
- 会場 鎌野海岸、鎌野自治会館(高松市庵治町)
- 講師 谷光承氏(かがわ海ごみリーダー)
- 講師アシスタント 畠山弘美氏(かがわ海ごみリーダー)
実施内容
8月2日(土)、鎌野海岸及び鎌野自治会館にて、「よく分かる!海ごみ調査講座」を開催し、17名が受講しました。本講座では、海ごみに関する座学や回収活動を通して海ごみの問題への理解を深めることを目的に開催されました。
〈レクチャー〉マイクロプラスチック調査について
はじめに、海ごみやマイクロプラスチックの調査方法について説明がありました。マイクロプラスチックは5mm以下のプラスチックのことで、海岸にある量を調べるための方法が紹介されました。調査では、縦横25cmの正方形の区画を設定し、深さ2cmまでの砂を採取します。その砂を5mm目のふるいにかけ、下に置いた水の入ったバケツに浮いた物質を網ですくい、マイクロプラスチックを選別します。説明の後、鎌野海岸へ移動しました。
〈現地調査〉海ごみ、マイクロプラスチック調査
鎌野海岸は、前週にクリーンアップが行われていたこともあり、一見ごみは少なく見えました。参加者は2グループに分かれて調査を開始し、まずは手で拾えるごみを回収しました。漂着物が帯状に集まる「満潮線」付近を中心に探した結果、釣り具、ゴルフボール、電子タバコの一部、肥料カプセル、かき養殖用のまめ管など、様々なごみが見つかりました。講師より、生活ごみだけでなく、まきびしやくるみなど池や川から流れてきたものも海岸に流れ着くと説明があり、ごみがどこから流れ着いてきたかを考えながら作業を行いました。その後、マイクロプラスチックのサンプル調査を行いました。縦横25cmの正方形の区画を作り、採取した砂をふるいにかけるとふるいの網目より小さな砂やマイクロプラスチックは下に落下し、ふるいの下の海水を入れたバケツに浮いている軽い物質を網を使って回収し、その中からマイクロプラスチックを探して回収しました。


〈屋内調査〉海ごみ、マイクロプラスチック調査
鎌野自治会館に戻り、回収したごみを分別し、種類を確認しました。その後、マイクロプラスチックの分別を行いました。事前に鎌野海岸と高尻海岸で採取して乾燥させたものを使い、グループに分かれてマイクロプラスチック観察シートを参考にしながら分別して個数を調べました。調査の結果、高尻海岸では硬質プラスチックが多く、鎌野海岸では肥料カプセルが多いことが分かり、海岸ごとに漂着するマイクロプラスチックの種類に違いがありました。受講者からは「2つの海岸を比較して地域によって差が出る」「海岸を見たときは奇麗だと思ったが、調査をすると予想以上にごみが多かった」「海をきれいにするのは大変」といった感想がありました。


〈海ごみについて〉
その後、海ごみの発生メカニズムについての説明がありました。人間が出したごみは、川を経て海へと流れ込み、細かく分解されてマイクロプラスチックとなります。これには添加剤や有害な化学物質が吸着しやすく、それを小魚が食べ、さらに大きな魚が食べることで、最終的に人間が食べると人体への影響があるのではないかというお話がありました。講座の最後に、「ごみを減らすことも大事だけど今日の講座で知ったことを人に話すことも大事」だとお話がありました。
講座終了後のアンケートでは、「マイクロプラスチックを分別する体験など、初めてのことができて学びにもなり、楽しかった」「マイクロプラスチックは色々な種類があることを知った」という感想が寄せられ、実体験を通じて海ごみについての学びを深められる大変有意義な講座となりました。



